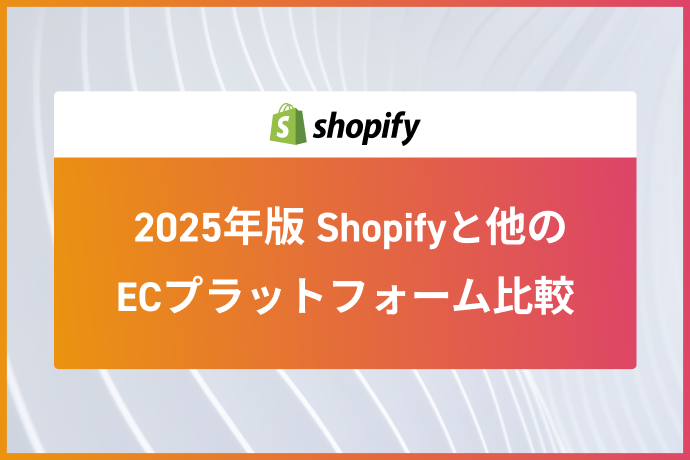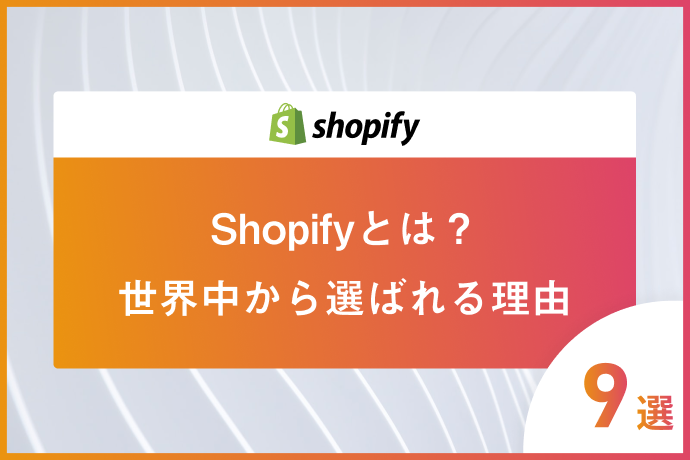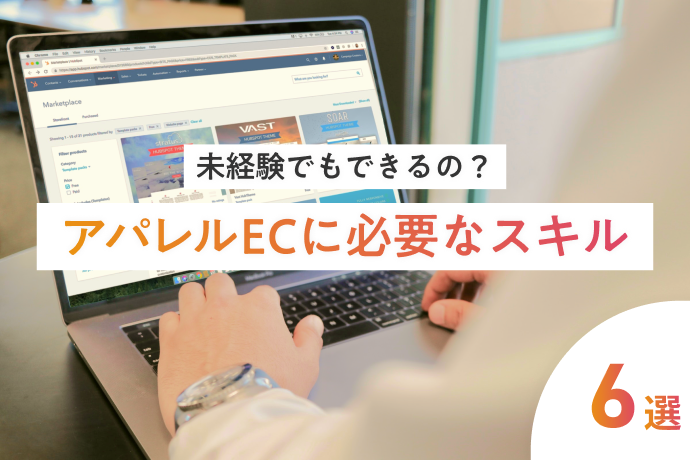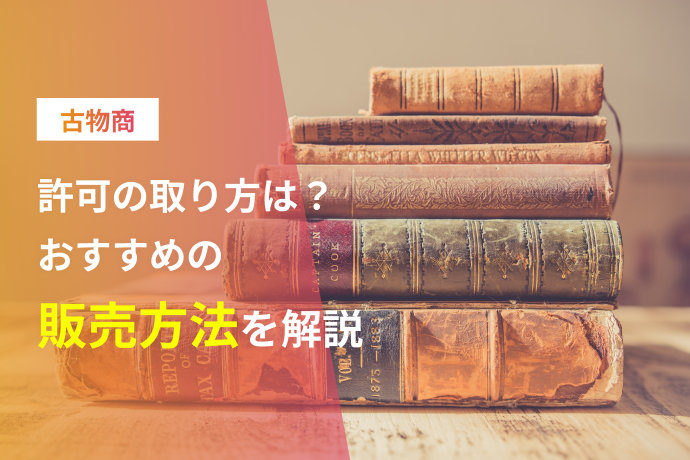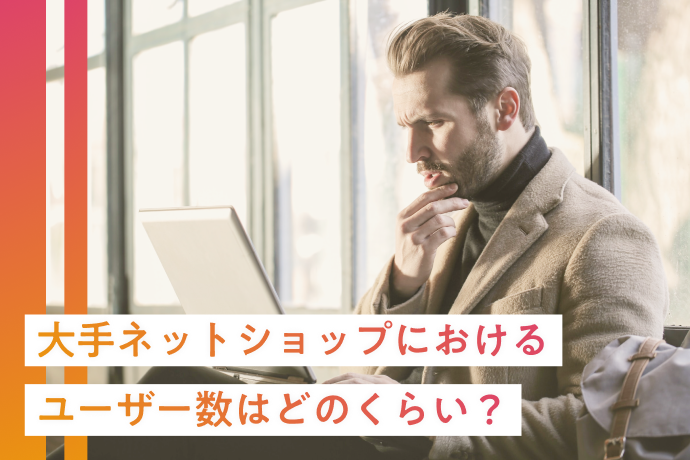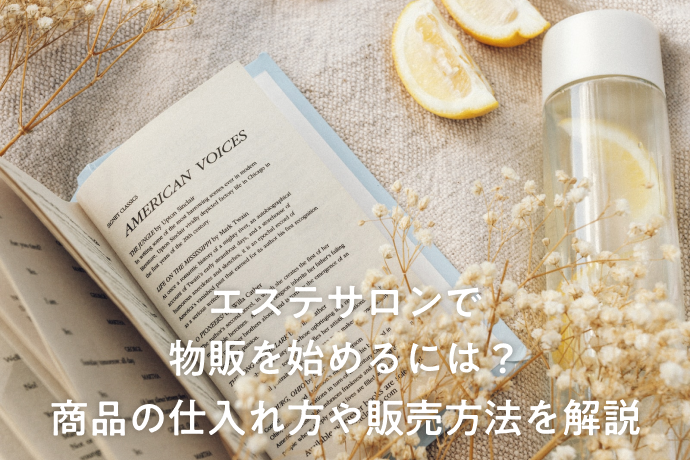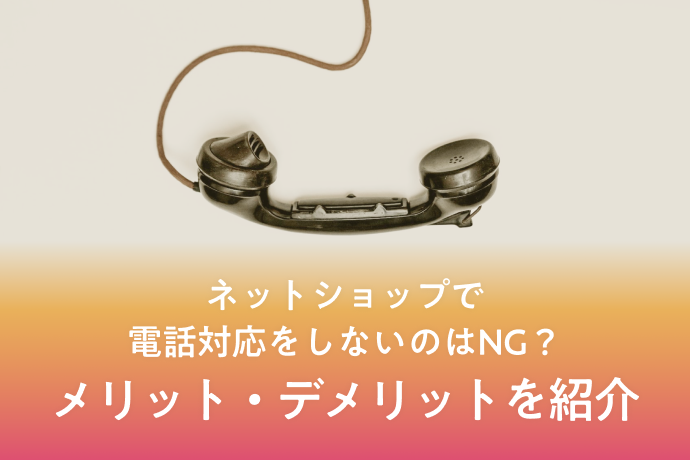ネットショップで食品を販売するのに必要な許可や資格を分かりやすく説明

ネットショップで食品を販売するには、事前に許可や資格を取る必要があります。
しかし、「許可・資格」と聞くと、難しそうだと感じてしまう方も少なくないでしょう。
そこで、この記事ではネットショップで食品を販売する際に必要な許可や資格について、分かりやすく説明していきます。
手続きの流れについても解説していきますので、具体的に「何をすれば良いのか」が明確になります。
手作りの食品や、仕入れた食品をネットショップで販売してみたいという方は、ぜひ参考にしてみてください。

ネットショップで食品販売をする際に必要な許可や資格
ネットショップで食品を販売する際に必要な許可や資格は、以下の2つです。
- 食品衛生責任者の資格
- 食品衛生法に基づく営業許可
上記に加え、これからネットショップで食品販売をしていきたいという方は、「食品販売に関する法律や条例」についての基本的な知識もつけておくと安心です。
では、これらの許可や資格、「食品販売に関する法律や条例」の内容について詳しくみていきましょう。
食品衛生責任者の資格について
まずは、ネットショップで食品販売をする際に必要な「食品衛生責任者の資格」について解説していきます。
「食品衛生責任者とは何か」また、「食品衛生責任者の資格を取得するまでの流れ」の2点について見ていきましょう。
食品衛生責任者とは?
食品衛生責任者とは、飲食店や食品工場など、食品の製造や販売を行なう事業に必要な資格です。
施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を設置することが義務付けられています。
食品衛生責任者の役割は主に、施設や調理器具、食品の取り扱いに衛生上の注意を払うことや、従業員へ衛生教育を行なうことなどです。
食品衛生責任者の資格は、都道府県知事等が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで取得できます。
なお、すでに飲食店などを営んでいて資格を所有している方は新たに申請する必要はありません。
また、栄養士や調理師などの資格を持っている方についても講習会を受講することなく、申請のみで資格の取得が可能です。
食品衛生責任者について詳しく知りたい方は、以下のページを参考にしてみてください。
食品衛生責任者の資格を取得するまでの流れ
食品衛生責任者の資格を取得するには、講習会を受講する必要があります。
ここでは、講習会の内容や、受講資格、費用などについて紹介していきます。
- 受講資格:17歳以上(地域によっては、現役高校生は受講不可)
- 費用:約1万円
- 講習会の内容:「公衆衛生学(1時間)」「衛生法規(2時間)」「食品衛生学(3時間)」の計6時間
地域によっては、最後に小テストがあります。 - 有効期限:なし
食品衛生責任者の資格は、受講さえすれば1日で取得できるものなので難易度はそこまで高くありません。
ですが、東京都や大阪府などの大都市では予約が埋まりやすいので、食品衛生責任者の資格が必要だと分かったら、早めに受講を申し込みましょう。
食品衛生法に基づく営業許可について
続いて、ネットショップで食品を販売する際に必要な「食品衛生法に基づく営業許可」について解説していきます。
ここでも「食品衛生法に基づく営業許可とは何か」また、「食品衛生法に基づく営業許可を取得するまでの流れ」の2点について見ていきましょう。
食品衛生法に基づく営業許可とは?
営業許可を取得するには、管轄する保健所へ営業許可申請を行ない、営業・加工施設の検査に合格する必要があります。
なお、営業許可の取得が必要なのは以下の32業種です。
| 種類 | 業種 |
|---|---|
| 調理業 | 1.飲食店営業 2.調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、 調理された食品を販売する営業 |
| 販売業 | 3.食肉販売業 4.魚介類販売業 5.魚介類競り売り営業 |
| 処理業 | 6.集乳業 7.乳処理業 8.特別牛乳搾取処理業 9.食肉処理業 10.食品の放射線照射業 |
| 製造業 | 11.菓子製造業 12.アイスクリーム類製造業 13.乳製品製造業 14.清涼飲料水製造業 15.食肉製品製造業 16.水産製品製造業 17.氷雪製造業 18.液卵製造業 19.食用油脂製造業 20.みそ又はしょうゆ製造業 21.酒類製造業 22.豆腐製造業 23.納豆製造業 24.麺類製造業 25.惣菜製造業(惣菜半製品を含む) 26.複合型惣菜製造業 27.冷凍食品製造業 28.複合型冷凍食品製造業 29.漬物製造業 30.密封包装食品製造業 31.食品の小分け業 32.添加物製造業 |
反対に、営業許可の取得が必要ない業種は、以下の通りです。
- 食品または添加物の輸入業
- 食品または添加物の貯蔵や運搬のみを行なう営業(冷凍、冷蔵倉庫業に該当しない)
- 常温で長期保存しても食品衛生上問題のない包装食品の販売業
- 合成樹脂を除く器具・容器包装の製造業
- 器具・容器包装の輸入または販売業
- 農業や水産業の採取業
- 集団給食施設(調理業務を委託している業者が許可を取得している場合、または1回20食未満の施設)
参照:営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報(厚生労働省)
上記の内容をまとめると、基本的には、自分で作った食品を販売したい場合や、仕入れた食品(輸入品や、常温で長期保存しても食品衛生上問題のない包装食品などを除く)を販売したい場合は、営業許可の取得が必要と考えて良いでしょう。
また、すでに飲食店を営んでいて、ネットショップでも商品(食品)を販売したいといった場合でも、別途営業許可が必要になることもあります。
まずは、保健所に相談してみましょう。
食品衛生法に基づく営業許可を取得するまでの流れ
ここからは、営業許可を取得するまでの以下の4つのステップについて詳しく解説していきます。
- 1.保健所に事前相談をする
- 2.営業許可申請を行なう
- 3.施設検査を受ける
- 4.営業許可証を交付してもらう
1.保健所に事前相談をする
販売したい商品や、営業・加工施設の設計図を工事前に持参し、まずは保健所に相談しましょう。
2.営業許可申請を行なう
必要な書類を準備し、保健所に営業許可申請を提出します。
必要な書類は以下の通りです。
- 営業許可申請書
- 場所の見取り図
- 内装の配置の平面図
- 営業設備の大要・配置図
- 登記事項証明書(法人が申請する場合のみ)
- 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合のみ)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類
3.施設検査を受ける
事前に保健所の担当者と施設検査を行なう日程を調整し、施設の工事が終わったら検査を受けます。
施設検査でチェックされる項目例は以下の通りです。
- 床や壁は掃除がしやすいか
- 蓋つきのゴミ箱が設置されているか
- トイレには手洗い場が設置されているか
- 厨房と客席は分けられているか
4.営業許可証を交付してもらう
検査に合格し、保健所で営業許可証の交付を受けたら、営業が開始できます。
食品販売に関する法律や条例について
ここからは、「食品販売に関する法律や条例」を6つ挙げていきます。
これからネットショップで食品販売をしていきたいという方は、先ほど紹介した許可や資格と併せて覚えておきましょう。
- 食品表示法
- 不当景品類及び不当表示防止法
- 計量法
- 健康増進法
- 米トレーサビリティ法
- 東京都消費生活条例
食品販売をする際には、食品に関する情報をラベルに表示することが義務付けられています。表示内容は、取り扱う食品によって異なります。
「食品表示法」については、以下のサイトを参考にしてみてください。
また、商品の内容や品質表示について定めた「不当景品類及び不当表示防止法」、適切な計量について定めた「計量法」、虚偽誇大表示を禁止する「健康増進法」なども知っておくと良いでしょう。
ほかにも、「米トレーサビリティ法」のように食品によって独自の法律が定められていることや、「東京都消費者生活条例」のように自治体ごとの条例もあります。
自分ですべての法律や条例を網羅するのは難しいので、ネットショップで食品販売をしてみたいという方は、まずは最寄りの保健所に相談してみましょう。
まとめ
今回は、ネットショップで食品を販売する際に必要な許可や資格について解説してきました。
基本的にネットショップで食品を販売する場合には、「食品衛生責任者の資格」と「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。
これらの許可や資格に加え、「食品表示に関する法律や条例」についての基本的な知識もつけておくと安心です。
ぜひ、この記事を参考にネットショップでの食品販売に挑戦してみましょう。