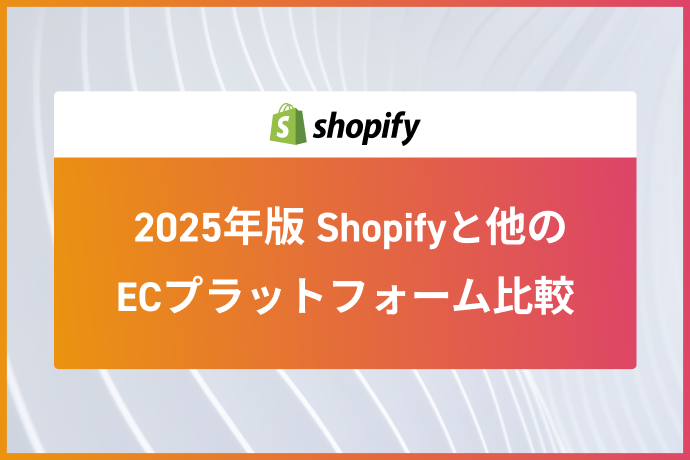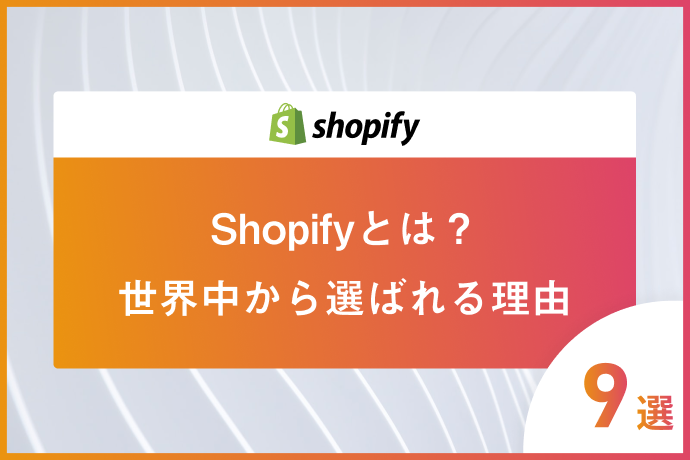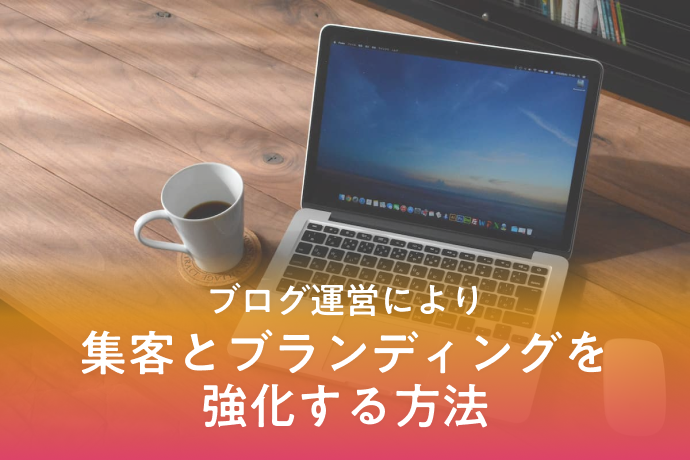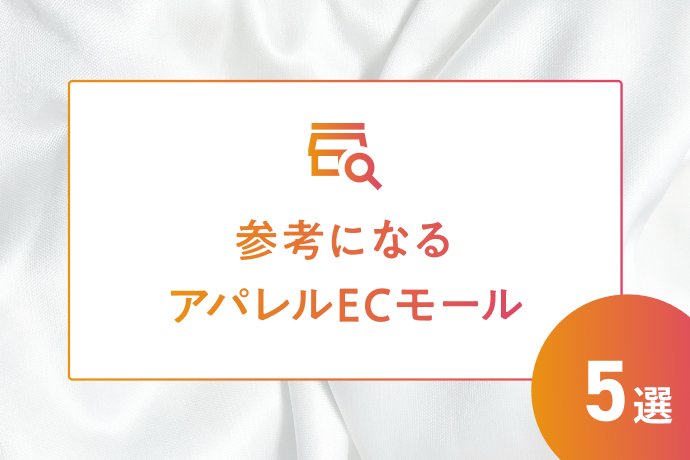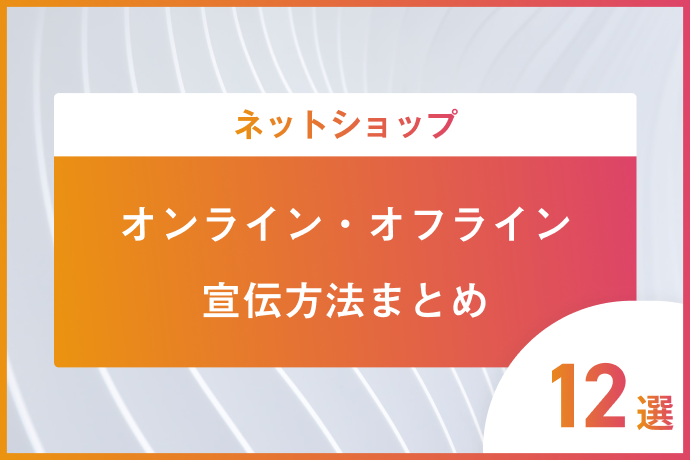ECサイト運営者は知っておくべき!電子帳簿保存法の知識と改正内容

これまで改正が繰り返されてきた「電子帳簿保存法」
令和3年度には、ECサイト運営者にも影響を与える大幅な改正が行われました。
しかし法律に関することのため、「そもそも電子帳簿保存法とは何?」「改正によって具体的に何が変わったの?」などあまりピンとこないという方も多いでしょう。
そこでこちらの記事では、 ECサイト運営者へ向けて、知っておくべき電子帳簿保存法の知識や改正内容についてわかりやすく解説していきます。
こちらの記事を読むことで、電子帳簿保存法についての理解を深めることができます。

電子帳簿保存法の知識
ここでは、ECサイト運営者が知っておくべき電子帳簿保存法の知識について解説していきます。
まずは「そもそも電子帳簿保存法とは何か」、「電子帳簿保存法で認められている保存方法」、「電子帳簿保存法の対象となる書類」の3点をしっかりと理解しましょう。
電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律です。
もともとこれらの書類は紙での保存が基本でしたが、業務の効率化などを目的に成立されました。
そして、これまで改正が繰り返されてきた電子帳簿保存法ですが、令和3年度に大幅な改正が行われました。
全ての事業者に強制適用される改正内容もあるので、ぜひ最後までご覧ください。
電子帳簿保存法で認められている保存方法
初めに、電子帳簿保存法で認められている保存方法を紹介します。
保存方法には、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子データ保存」の3つがあり、それぞれに「保存要件」があります。
保存要件などの規定を守らないと、場合によっては罰則が科される可能性もあるので注意しましょう。
ここでは、それぞれの保存方法について説明していきます。
保存要件についてわかりやすく解説されたページも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
電子帳簿等保存
電子帳簿等保存は、会計ソフトなどで電子的に作成した帳簿や書類を電子データのまま保存することを指します。
スキャナ保存
スキャナ保存は、紙で受領した・作成した書類をスキャナで電子化して「画像データ」として保存することを指します。
電子データ保存
電子データ保存は、電子的に受領した・送付した取引情報を電子データのまま保存することを指します。
電子帳簿保存法の対象となる書類
では、どのような書類が電子帳簿保存法の対象となるのでしょうか。
対象となる書類は「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類です。
ここでは、それぞれの書類の具体例と保存方法を紹介していきます。
なお、書類の種類によって保存方法が異なるということを覚えてきましょう。
国税関係帳簿
国税関係帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳などの帳簿データが該当します。
国税関係書類
国税関係書類には、「決算関係書類」と「取引関係書類」が含まれます。
さらに「取引関係書類」は「自社で発行したもの」と「相手方より受領したもの」に分けられます。
- 決算関係書類:貸借対照表、損益計算書、棚卸表、試算表など
- 取引関係書類(自社で発行):見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書、契約書などの控え
- 取引関係書類(相手から発行):見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書、契約書など
電子取引
PDFファイルなどで送られてきた見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書、契約書などが該当します。
電子帳簿保存法の改正内容
ここからは、ECサイト運営者が知っておくべき電子帳簿保存法の改正内容について解説していきます。
注目すべきは、先ほど紹介した3つの保存方法の「保存要件」の部分です。
では、変更された点を保存方法ごとにチェックしていきましょう。
電子帳簿等保存に関する改正内容
電子帳簿等保存に関する改正内容は以下の通りです。
- 税務署長の事前承認制度が廃止された
- 保存区分が、これまでと同等の要件が求められる「優良な電子帳簿保存」と最低限の要件が求められる「その他の電子帳簿保存」の2つになった
- 優良な電子帳簿に対する「過少申告加算税の5%軽減」措置が整備された
中でもポイントは「税務署長の事前承認制度の廃止」と「その他の電子帳簿保存」が加わった2点です。
まず、「税務署長の事前承認制度の廃止」についてです。
これまでは、国税関係の帳簿や書類を電子データで保存する際には、保存しようとする時期の3ヶ月前までに税務署に届け出をする必要がありましたが、今回の改正により不要になりました。
また、「その他の電子帳簿保存」区分が加わったことで「訂正履歴」などの要件が不要になり、導入のハードルが大幅に下がりました。
スキャナ保存に関する改正内容
スキャナ保存に関する改正内容は以下の通りです。
- 税務署長の事前承認制度が廃止された
- タイムスタンプ要件と検索要件が緩和された
- 適正事務処理要件が廃止された
- 不正行為への罰則が強化された
中でもポイントは「タイムスタンプ要件と検索要件の緩和」と「適正事務処理要件の廃止」の2点です。
まず、「タイムスタンプ要件と検索要件の緩和」についてです。
タイムスタンプ要件では、受領者の自署が不要となり、スキャンを行える期間が最長で約2ヶ月に延長されました。
さらに、訂正や削除の履歴を残すことでタイムスタンプの付与が不要になります。
検索要件については、記録項目が「取引年月日・取引金額・取引先」の3点のみになりました。
しかも、税務職員による電磁的記録のダウンロードの求めに応じられる場合は、「範囲指定」などの機能も不要になります。
また、「適正事務処理要件」とは、相互チェックや定期検査を行うといった内容のものでしたが、こちらの要件も今回の改正により廃止されました。
スキャナ保存に対して、以前よりも簡素化されている点は非常に嬉しいですね。
電子データ保存に関する改正内容
電子データ保存に関する改正内容は以下の通りです。
- 電子取引におけるデータ保存の義務化
- タイムスタンプ要件と検索要件が緩和された
- 不正行為への罰則が強化された
中でもポイントは「電子取引におけるデータ保存の義務化」です。
これまでは、電子取引に該当するデータは、印刷して紙媒体で保存することも容認されていました。
しかし、今回の改正により令和4年1月1日以降に行われる電子取引においては、原則、電子データのまま保存することが必要です。
これは、全ての事業者に適用されます。
なお、電子データ化への早急な対応が困難なケースも考慮し、令和4年1月1日から2年間の電子取引情報については、宥恕措置(ゆうじょそち)が設けられています。
よって、一定の要件を満たしている場合は引き続き出力した書面での保存が認められます。
令和6年1月1日以降は、全ての事業者に対し電子データ保存が義務となるので、余裕を持って準備に取り掛かりましょう。
まとめ
今回は、ECサイト運営者へ向けて、電子帳簿保存法の知識や改正内容について解説してきました。
今回の改正内容で最もECサイト運営者に影響を与えるのは、電子データ保存に関する改正でしょう。
令和6年1月1日から全ての事業者に対して、電子取引の電子データ保存が義務化されます。
保存要件をしっかりと確認し、ソフトの導入など必要な準備を進めていきましょう。